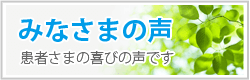サッカーの南野拓実選手が損傷した前十字靱帯(ACL)は膝の前方移動と回旋を制御する極めて重要な組織で、前十字靭帯の損傷はスポーツにおいて重傷とされ、復帰まで一年以上要する事もある。関節包内靱帯の為、自然治癒は見込めず、復帰には自身のハムストリングスの腱を用いた手術が主要な選択となる。
大腿骨外側顆の内側面から脛骨高原前顆間区に付着している前十字靱帯は主にⅠ型コラーゲンで構成され、従来の二束(前内側束・後外側束)概念に加え、三束説やトルクを伝える螺旋的配列もあり、骨への付着部は個人差があり広く複雑であるが、この付着部の個人差を考慮した再建術をすることにより術後の復帰や再発防止へ大きく影響することがわかっている。
膝外反(Knee-in)、脛骨の内旋または外旋、大腿四頭筋の急激な収縮がACLへの負荷となります。
かつてACLは、直径約10mm程度の「円柱状の太い束」だと思われていました。しかし、実際に関節内を詳しく観察すると、中央部は非常に薄いことが分かっています。厚さはわずか 2〜3mm 程度、幅が 10〜15mm ほどある、平らな帯のような形をしています。大腿骨から脛骨へ向かう途中で 約90度ねじれているのが最大の特徴です。膝を伸ばすとピンと張って平らになり、膝を曲げるとねじれながら折り畳まれるような動きをします。昔は手術の際に円形の穴を骨に開けて再建していましたが、今は本来のC字やリボンの位置にいかに近づけるかが重視されます。ACLが円柱状だと、膝を伸ばした時に骨の隙間に挟まってしまうことがありますが、リボン状であれば薄いため、狭い隙間(顆間窩)でもスムーズに収まります。
ACLは線ではなく面で骨に付着しているため、回旋に対する抵抗力が非常に強い構造になっています。またACLは単なる紐ではなく、高度なセンサーとしての役割を担っていて膝の角度や動きのスピードを脳に伝える役割もあります。ACLを損傷すると膝が物理的に緩むだけでなく、このセンサー機能が失われます。その結果、脳が「膝をどう制御していいか分からない」状態になり、再受傷のリスクが高まります。
前十字靭帯の原型は、約3億年以上前、石炭紀の両生類や初期の爬虫類が陸に上がった頃には既に存在していたと考えられています。
陸上での移動には膝関節が必要でしたが、単に骨を乗せるだけでは滑り落ちてしまいます。そこで、骨同士をクロスさせて繋ぎ止める十字構造が発生しました。
魚類から四肢動物へ進化する過程で、膝の安定装置としてこの十字構造は非常に優秀だったため、基本的なメカニズムは数億年間大きな変更なしに現代のヒトまで受け継がれています。
四足歩行動物のヒトとの最大の違いは、常に膝が屈曲(曲がった)状態で荷重がかかるかという点です。ヒトは直立二足歩行を獲得したことで、膝を「真っ直ぐ伸ばし切る」ことができるようになりました。この時、大腿骨と脛骨の間の隙間は非常に狭くなります。もしACLが丸太のように太いままだと、伸ばした時に骨に挟まって(インピンジメント)邪魔になってしまいます。
そのためヒトのACLは強度は保ちつつ、隙間に収まりやすい非常に薄く扁平なリボンのようなスリムな形状へと変化していったと考えられています。
近年は前外側靭帯(ALL)と呼ばれる靭帯にも注目されています。ALLは膝関節の回旋の安定化に重要な役割を果たし、ACL損傷時にこの前外側靭帯(ALL)も損傷していることが多くACL再建手術で前外側靭帯(ALL)の損傷度合いが重要となります。前外側靭帯は外側側副靭帯の前方に位置し、大腿骨外側上顆から脛骨前外側面に付着します、
ACLは、解剖学的にはリボン状の扁平な組織であり、生理学的には膝の動きを脳に伝える精密なセンサーです。最新のスポーツ医学では、筋力だけを見るのではなく、脳・神経系を含めたコントロール能力と外側の支持組織(ALLなど)を含めた包括的な安定性が重視されています。